イベントレポート 「DXトークセッション:AIはDXの未来を拓く鍵となるのか? DXの未来予想とここから始める行動計画」
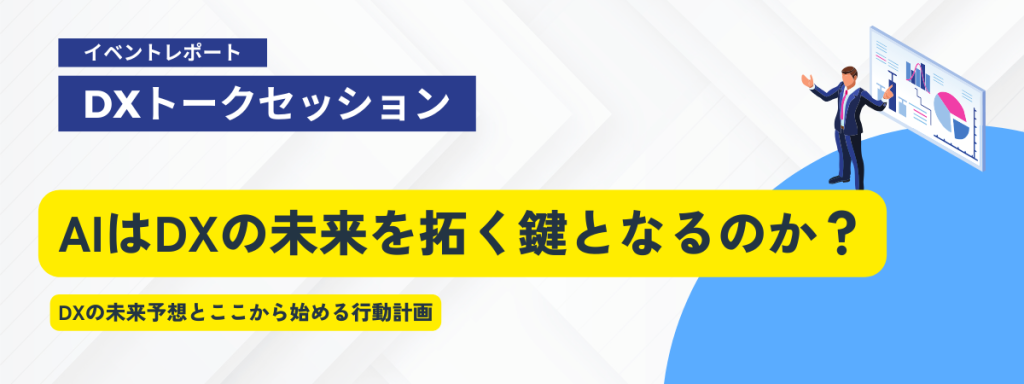
中小企業DX推進研究会では、2025年9月26日に 「AIはDXの未来を拓く鍵となるのか? DXの未来予想とここから始める行動計画」 をテーマに、ディスカッションを行う会員定例勉強会を開催いたしました。
今回は、中小企業DX推進研究会の発足後の5年間のDXの歩みを振り返りつつ、生成AIの活用やDXの未来について幅広い視点で議論が行われました。
2025年9月26日 (金) 16:30 ~ 17:30 開催
テーマ: 「AIはDXの未来を拓く鍵となるのか? DXの未来予想とここから始める行動計画」
Contents
Q1. ここ5年ほどの <所内> の変化について教えてください。
まずは、各事務所の 「所内の変化」 について振り返りました。
このようなディスカッションがされました📝
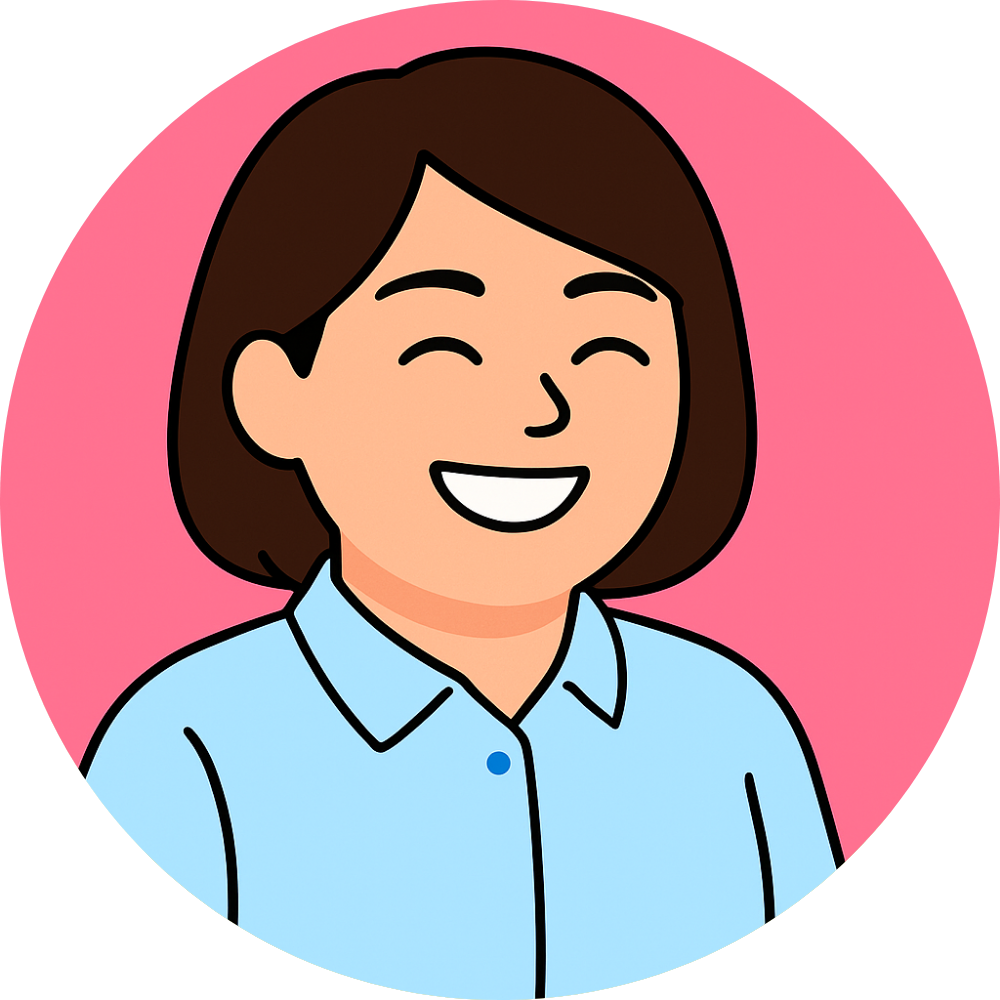
事前アンケートでは、業務標準化の推進、テレワークやフレックス制度の導入、遠方顧問先とのWeb面談の定着といった回答が多く寄せられました。
さらに、DocuWorksやクラウドサインによるペーパーレス化、RPAの活用、クラウド会計ソフトの導入、Chatworkやkintoneなど、新たなツールの採用といった具体的な変化も挙げられていました。

この5年間で特に印象的なのは、クラウド会計の利用率の急上昇です。マネーフォワードやfreeeを導入する事務所が増え、単なる会計処理から『入力業務をなくす』方向に意識が変わってきたのではないでしょうか。また、テレビCMの影響もあってか、kintoneの利用も広がっています。Chatworkも同様で、所内のコミュニケーションの在り方が大きく変わった5年間でした。

世の中全体ではDXが進展していますが、従来のやり方が根強く残っている部分もあり.. 所内の意識が完全に変わり切ったとは言い難いですね。ですが、少しずつツールの活用場面を増やそうと検討を進めている最中です。

遠方の顧問先とのWebを使った会議は確実に増えました。先方へ出向いての打ち合わせが難しい場合には、オンラインに切り替えるなど、面談回数自体は変わらないものの、実施方法の選択肢が広がったという感覚ですね。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
全体として、ペーパーレスやクラウドサービスの導入が一気に進んだ印象の5年間でした。クラウド会計の利用率は急上昇し、これまで人手で行っていた入力作業をなくすという意識が浸透してきています。また、kintoneやChatworkといったクラウドツールも普及し、業務の進め方そのものが刷新されつつあります。
ただし、すべてがスムーズに進んだわけではありません。従来型の方法を完全に捨て切れていない事務所も少なくなく、紙や対面に依存した業務も依然として残っています。つまり、この5年間は “変化と継続が混在する過渡期” だったのです。これから先は、新しい仕組みをいかに所内に根付かせて、標準化していけるかが問われていくでしょう。
Q2. ここ5年ほどの <お客さま> の変化について教えてください
次に 「お客さま側の変化」 について意見が交わされました。
このようなディスカッションがされました📝
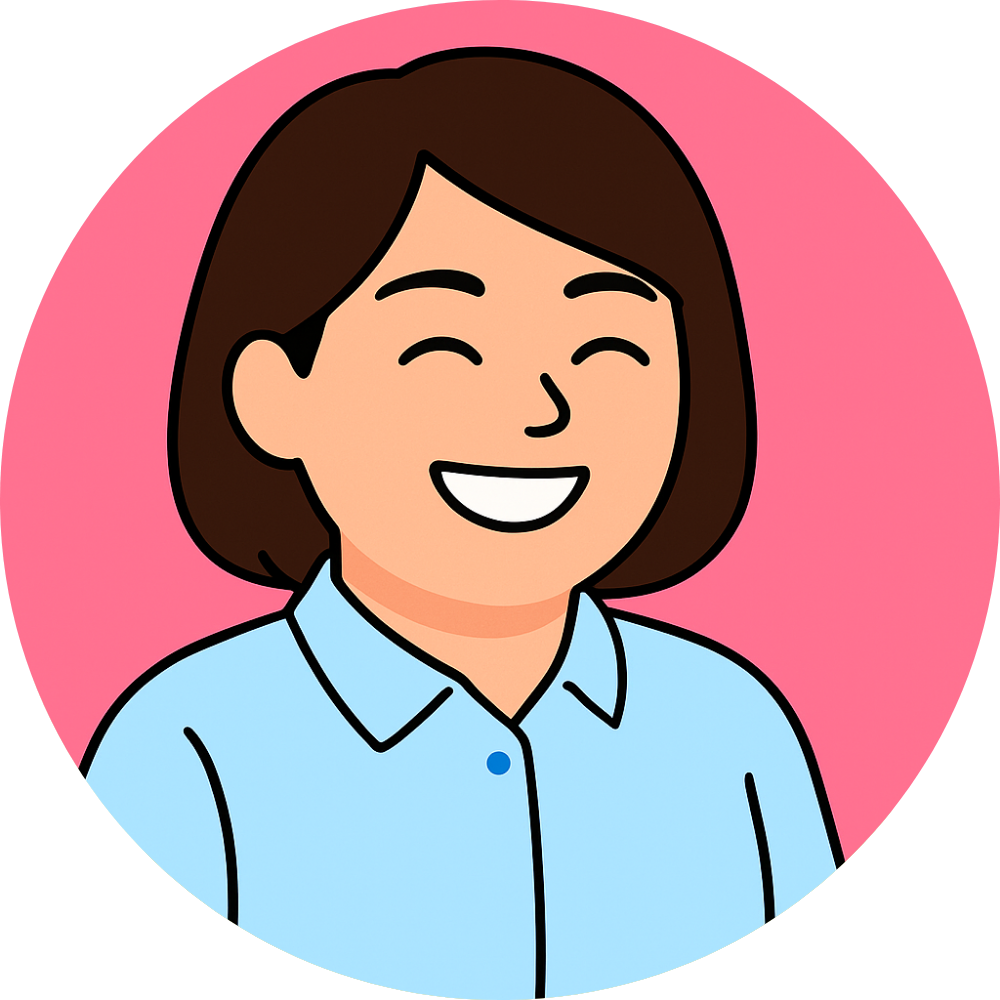
多くの回答で共通していたのは、資料回収方法の電子化です。紙から電子へ移行する顧客が増え、クラウド上でのデータ提出が日常的になりつつありますね。

たしかに、この5年で領収書や契約書類をクラウド経由でやり取りするケースが一般的になりました。ただし紙でのやり取りが完全になくなったわけではないため、結果的に “対応パターンが増えた” とも実感しています。なかなか難しいところですね.. 。
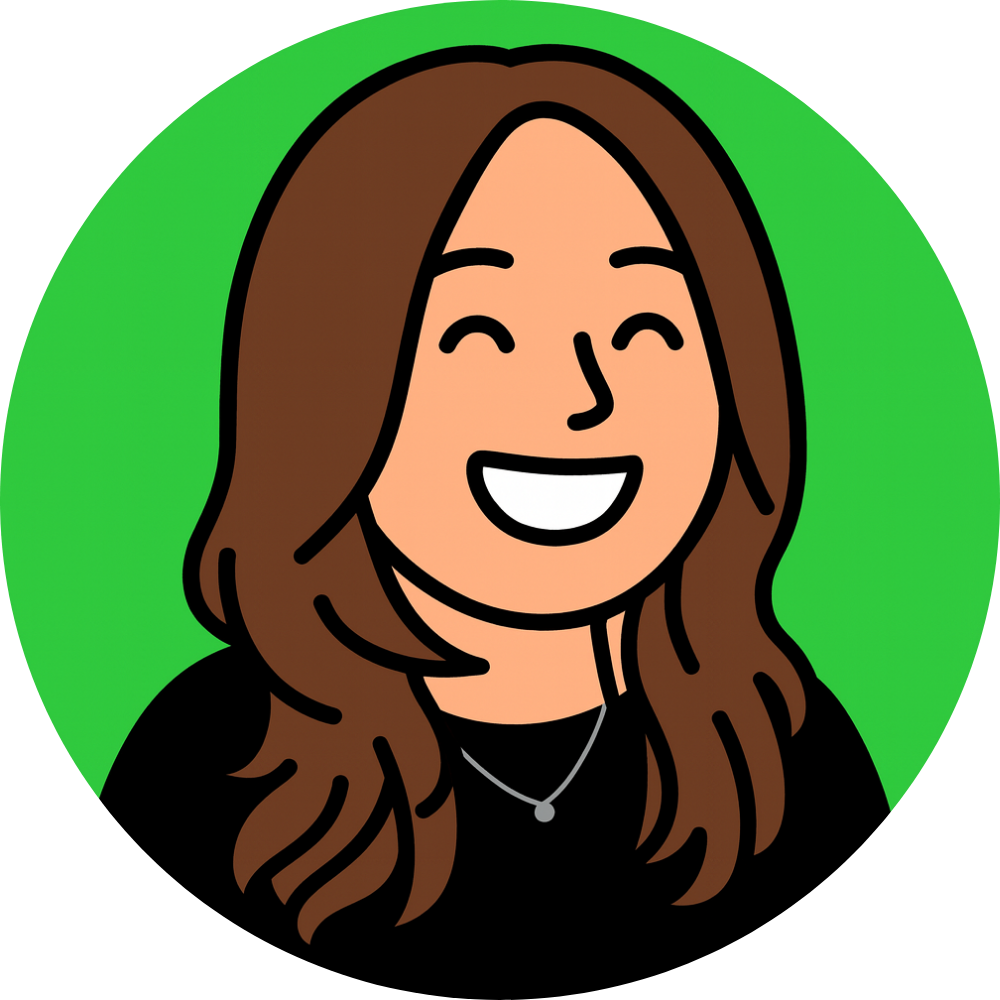
お客さまのクラウド環境下に資料があって、第三者である私たちが直接ログインして受け取りに行くこともありますが、IDをいくつも所有することになるなどセキュリティ面でも難しいです。結果として、完全にデジタルに移行できるケースは少なく、紙とデジタルが混在する状態が続き、所内の対応工数はむしろ増える場合もあります。

私たちの事務所でも、これまでは紙のみでの対応であったお客さまでいよいよ電子での体制に切り替わったという先において、おもにデジタル、一部は紙のままという証憑の預かり方となってしまい、突合のため電子も紙も見なくてはならなくなってしまった、なんて状況もあります。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
顧客対応の幅が広がったことは確かですが、それは同時に事務所にとって負担が増えることにも繋がります。デジタル提出が増えた一方で紙も依然として残り、結果的に “対応パターンが増えただけ” という印象もあります。顧客がデジタル化を進めてくれることはありがたい反面、事務所側でセキュリティや運用ルールを検討する必要が増し、むしろ業務が複雑化している側面もあります。
大規模な事務所では、紙対応とデジタル対応を行うチームを分けるといった戦略も可能でしょうが、多くの現場ではそこまでの体制を取るのは難しいのが現実です。したがって今後は、”顧客に合わせる柔軟性” を持ちながらも、いかに内部の標準化を進め、効率性を損なわないように工夫するかが最大の課題になると考えています。
Q3. 今後の生成AI導入について教えてください
次のテーマは「生成AIの導入」についてです。
このようなディスカッションがされました📝
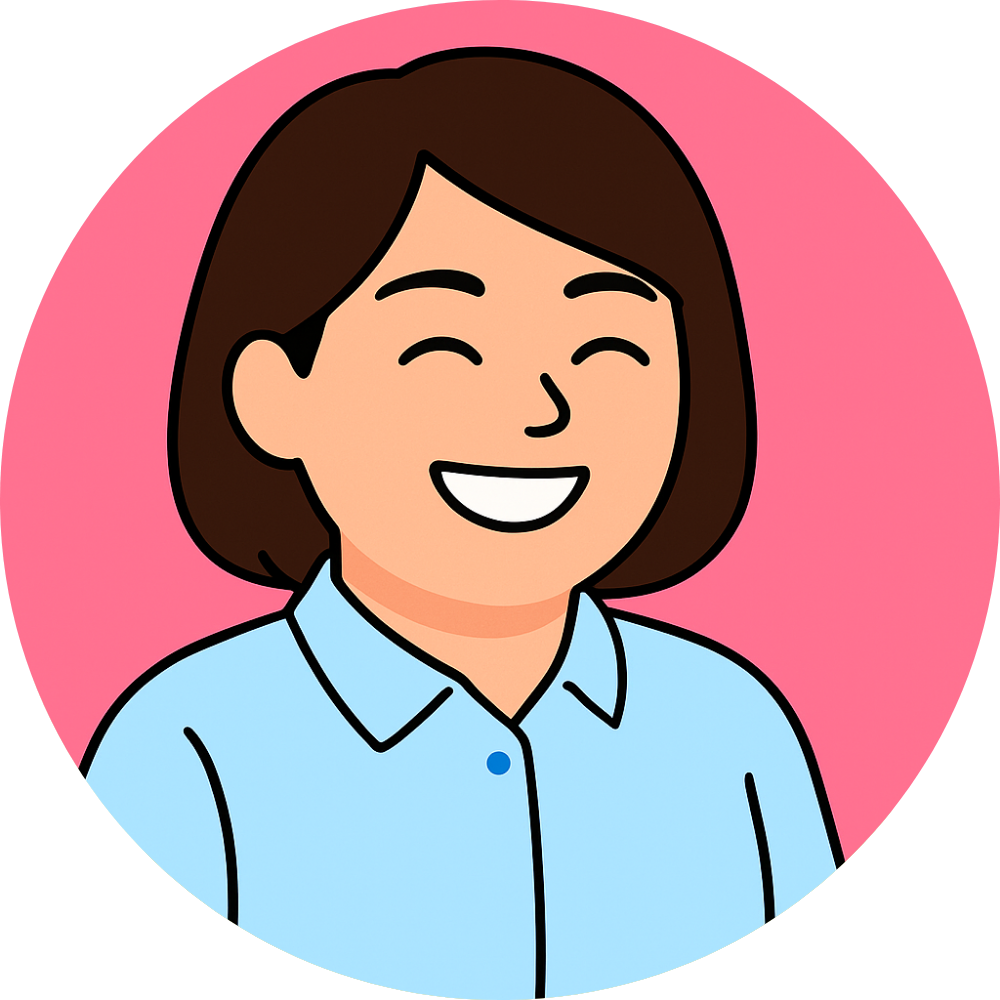
アンケートでは 「社内で統一したAIツールを利活用している、または導入予定」 との回答が目立ちました。

私たちのグループでは Google Workspace を導入し、Gemini や NotebookLM を利用しています。Google Workspace を導入した理由としては、学習データを外部に収集されない安心感、サービスが急に終了しない安定感があります。他の事務所でも同様の理由から Google Workspace を導入する例が増えているという声も聞いています。

私たちの事務所では、AIをまだ触ったことがない職員もいて.. 。そこで、まずは『全員が一度はログインする』という働きかけをしました。

私たちは、システムメンバーで複数のAIツールを検証し、ITリテラシーが低い人でも使えるようなAIチャットツールを導入しました。どの作業に使用するか、どのように扱うかといった用途は限定せず、まずは職員全体で試すことを優先しています。

業務利用だけでなく、日常的な利用も推奨しています。まずは抵抗感をなくし、どのようなことができるのか発想力を養ってらいたいなと考えており、自然に活用できる環境をつくることを重視しています。
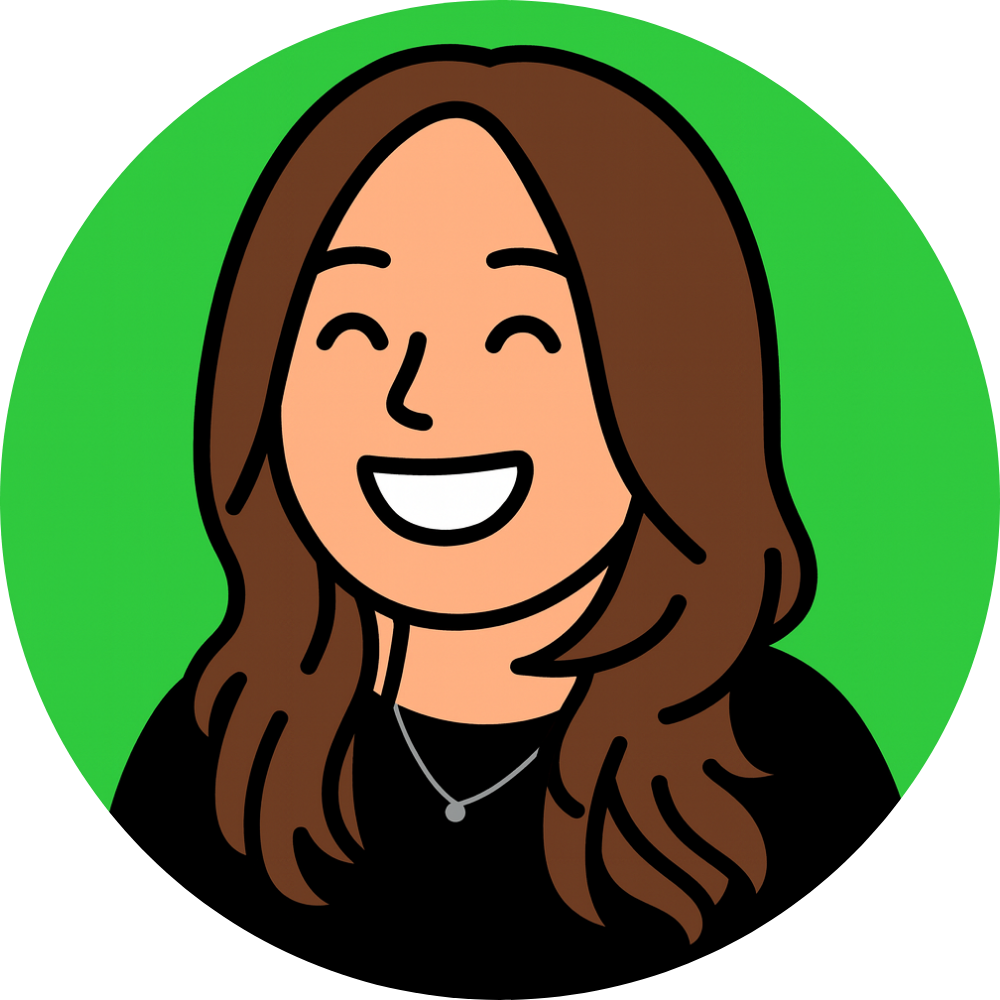
全社でどれを使いましょうなどという方針はいまのところ定まっておらず、誰がどのツールを使っているか把握しきれていませんが、多くの職員は文章作成に使っている印象です。最近はプロンプト不要のAIも試しており、Excel集計の自動化に可能性を感じています。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
生成AIについては、各事務所が模索を続けている段階です。私たちのグループでは Google Workspace を中心に Gemini や NotebookLM を導入していますが、理由は “安心して長期的に利用できる” という点に尽きます。学習データが外部に持ち出されるリスクが少なく、サービスの持続性も高いため、安心して社員に使わせることができます。
ただし、AIの活用はどの事務所でもまだ均一ではありません。プロンプトを駆使できる人とそうでない人では使いこなしに差が出やすく、全員に同じレベルで浸透させるのは難しいのが実情です。その意味では、パッケージ化されていてスキルに左右されにくいAIツールの方が、現段階では有効だと考えています。AIはあくまで “業務を補助する道具” と考えるのがいいように思います。仕訳入力や集計作業など実務でのAI活用は、プロンプトを検討したり一から設計していくのではなく、これからソフトベンダーが発表するであろう機能に委ね、私たちはより高度な判断や付加価値業務に力を注ぐべきでしょう。
Q4. 5年後、10年後の未来についてDXや生成AI、そして社会全体はどのように変わっていると予測しますか?またそこにどんな課題やチャンスがあると考えますか?
最後に、DXとAIが浸透した未来について議論が行われました。
このようなディスカッションがされました📝

マイナンバーカードの普及・浸透によって、給与計算や社会保険の手続き、住民税の算定など事務処理はほぼなくなり、労務的な業務がすごくコンパクトになるかなと考えています。また、納税手続きについても同様で、今も銀行窓口に出向いて行う業務は確実に減少していますし、オンライン完結が標準になると予測しています。
さらに、巡回担当者の話では、これまでオフィスに戻ってからまとめていた報告書や議事録も、AIを活用して、移動中の車の中で声で話したことを基に作成する者もいるようです。今後は業務の効率化はもちろんですが、職員が “本当に付加価値を生む業務” に集中できる環境が整っていくのではないでしょうか。

技術の進歩がどれほど加速しても、最終的に成果を決めるのは人間と考えています。そう考えると、AIの利用によって事務処理が自動化される一方で、それをどう業務に組み込み、成果につなげるかは人材の力量にかかっていると言えるでしょう。だからこそ、今後の10年は “人間力” がより強く問われる時代になると考えています。
新しい技術に適応する柔軟性、社内外の人と協働するコミュニケーション力、そしてお客さまに信頼いただける誠実さや責任感といった資質が、次の時代の会計事務所にとって欠かせないスキルだと感じています。そこで、自社でも人間力向上をテーマにした委員会の立ち上げも検討している段階です。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
AIが広がれば仕事がなくなるのではないか、という懸念はよく耳にします。しかし、歴史を振り返ると、パソコンが普及しても新しい仕事が生まれ、ペーパーレスが進んでも別の業務が生まれてきました。AIも同じで、業務が “なくなる” のではなく “形を変える” だけなのだと考えています。
そのうえで重要なのは、自社がどのような未来像を描くかです。闇雲に最新技術を追いかけるのではなく、目指す方向性を定め、そこに沿って業務を進化させていく必要があります。AIは知識習得や効率化の面では大いに役立ちますが、思考力やコミュニケーション力といった “人間にしかできない部分” は引き続き不可欠です。つまり、AIは人の力を補強する存在であり、最終的に成果を決めるのは人材の成長と組織の戦略性なのです。
まとめ
今回のセッションでは、所内の変化から顧客対応、生成AIの導入、そして5年後・10年後の未来予測まで、多角的に意見が交わされました。議論を通じて見えてきたのは、DXやAIは業務を消すのではなく、その形を変えて新しい価値を生み出す存在であるという共通の認識です。
参加者の声からは、デジタル化やAIの浸透が進む一方で、人間の思考力やコミュニケーション力といった “人ならではの力” がこれから先の時代に、一層重要になることが示されました。AIと人の役割分担をどう描くかが、事務所経営の未来を左右する大きな課題と言えるでしょう。また、顧客対応の多様化や所内業務の変革といったテーマからも、柔軟性と標準化の両立という課題が浮かび上がりました。変化の中にあっても、現場に即した工夫を積み重ねていくことが不可欠です。
そして、本イベントをもって 「中小企業DX推進研究会」 としての活動は一区切りを迎えることとなりました。これまで多くの皆さまにご参加いただき、率直な意見交換を通じて積み上げてきた知見は、研究会の大きな財産です。活動はクローズとなりますが、ここで得られた学びやネットワークは今後も生き続け、次のステージでのDX・AIの取り組みに必ずつながっていくはずです。本セッションでの議論が、皆さまの次の一歩を考える一助となれば幸いです。
