イベントレポート 「DXトークセッション:DX推進の軌跡を振り返る ~ 変わったこと、変わらなかったこと。DX達成に向かって私たちは正しい道を歩んでいるのか? ~」
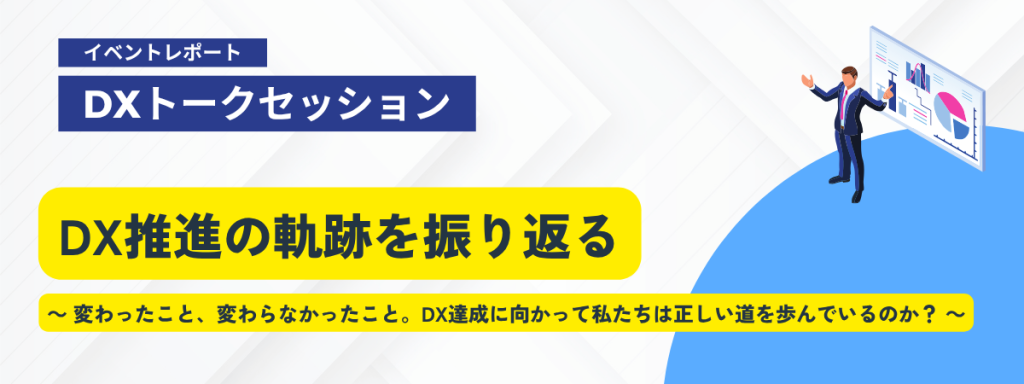
中小企業DX推進研究会では、2025年7月25日に 「DX推進の軌跡を振り返る」 をテーマに、ディスカッションを行う会員定例勉強会を開催いたしました。
今回は、研究会の立ち上げからおよそ5年間の歩みを振り返りながら、DX推進の現状と今後の方向性について意見を交わしました。
2025年7月25日 (金) 16:30 ~ 17:30 開催
テーマ:DX推進の軌跡を振り返る
Contents
Q1. DX推進、DXの考え方において貴所に最も近いスタンスを教えてください。
まずは、各事務所のDX推進に対するスタンスをテーマに意見交換を行いました。
事前アンケートでは、以下の7つの選択肢の中から最も近いものを選んでいただきました。
・経営として明確なDX方針を掲げており浸透している
・経営として明確なDX方針を掲げているが具体的には未着手、または仕掛の状態
・自社業務のIT化・効率化を優先している
・顧客支援の文脈でDXに取り組めている
・”DXとは何か” を模索している段階
・正直、DXには疲れてしまった (または疑問を感じている)
・経営層は前向きでも、従業員側が後ろ向き、またはその逆
アンケートの結果、「経営として明確なDX方針を掲げており浸透している」 や 「自社業務のIT化 ・ 効率化を優先している」 と回答した事務所が最も多いことがわかりました。
一方で、“DXとは何か” を模索している段階や、DXに疲れを感じているといった声も一定数寄せられています。
このようなディスカッションがされました📝
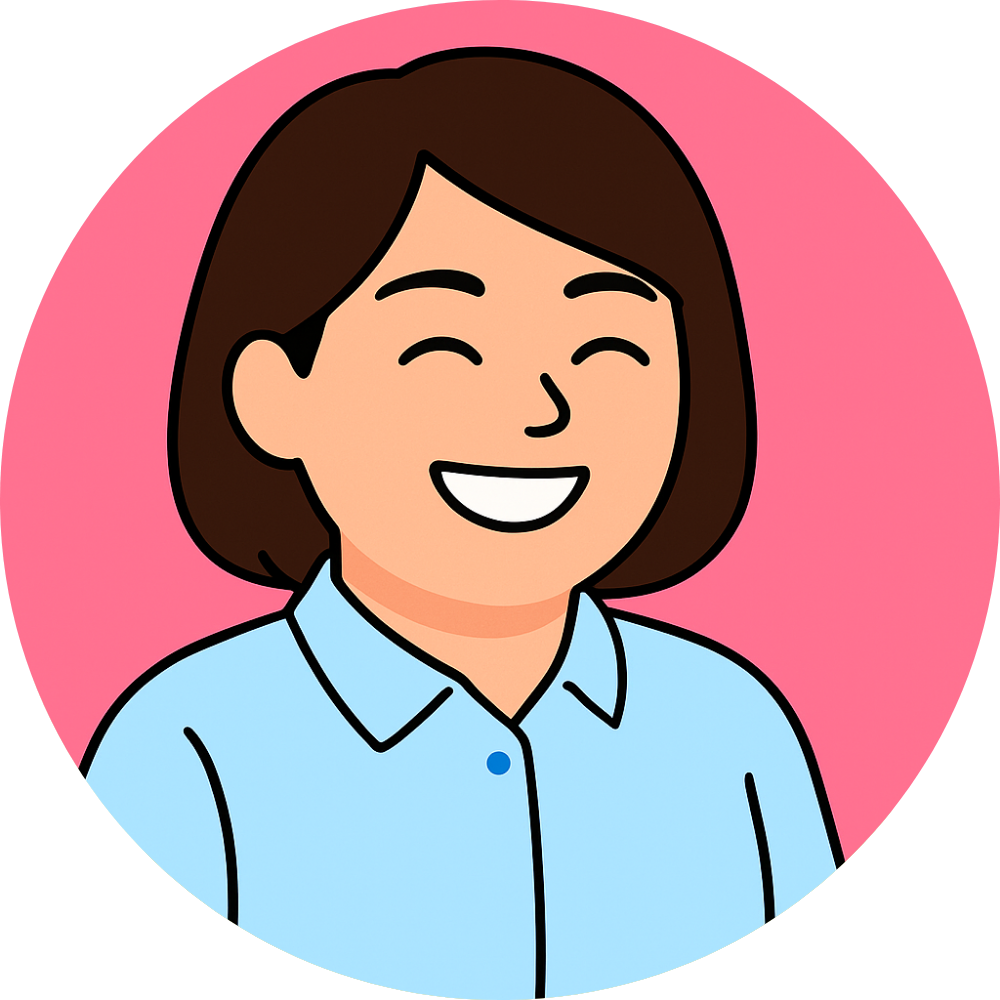
経営方針としてDXを掲げて浸透している、という回答が多かった一方で、模索中や疲弊感を覚えるという声もありました。

DXという言葉自体は当たり前のように使われるようになりましたが、その本質と現場での使われ方にはズレがあるように感じます。本来はデジタル技術を活用して新しい価値を創造することすなわちトランスフォーメーションが目的ですが、実際には、これまで行ってきたIT化やシステム化のことを “DX” と呼んでいるだけのケースも多いのではないでしょうか。

自分たちもDXやIT化を進めてはいますが、『何のためにやっているのか』を常に意識しないと、手段が目的化してしまうと感じます。お客様からもDXやクラウド会計に関する相談を受けることがここ数年で増えました。ただ、実態はIT化にとどまっていることが多く、DXによる価値創出までは至っていない印象です。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
ここ数年でDXの解釈は広がり、取り組みの内容や深度も事務所ごとに多様化してきました。その中で、最も大きな変化の一つとして挙げられるのがウェブ会議の浸透です。かつては訪問が中心だった業務がオンラインで完結するようになり、移動時間やコストなど負担が大きく減少しました。今ではオンラインミーティングは日常化し、コミュニケーションのスタイルそのものが大きく変わってきています。
このような “働き方の変化” こそがDXの持つ本来の価値を示しており、私たちはこの変化を次の価値創造につなげていくことが重要だと感じています。
Q2. 今後の 「DX」 とは、どのような方向へ進んでいくと思いますか?
続いては、DXの今後の動向について議論しました。
まずは2020年から2025年の社会情勢とIT・DX動向をかんたんに年表へ整理しました。
| 年 | 社会情勢 | IT・DX動向 |
| 2020年 (令和2年) | ・新型コロナウイルス拡大 (パンデミック) ・日本で緊急事態宣言 (4月) ※5月には解除緩和 ・東京五輪延期決定 | ・テレワーク導入が急拡大 ・Zoom等オンライン会議普及 ・デジタル庁創設の検討開始 ・電子帳簿保存法の改正 (10月) (キャッシュレス決済の場合に領収書が不要) |
| 2021年 (令和3年) | ・東京五輪 (無観客) ・ワクチン接種が本格化 (2月~) ・飲食・観光など一部業界回復の兆し | ・デジタル庁発足 (9月1日) ・自治体のオンライン手続き強化 ・中小企業にもIT導入補助金注目 |
| 2022年 (令和4年) | ・ロシア、ウクライナ侵攻 ・物価高・エネルギー危機拡大 ・感染症 「第7波」 到来 (7月・オミクロン) | ・DX推進ガイドライン改訂 ・IT人材の不足が深刻化 ・ChatGPTなど生成AIの登場 |
| 2023年 (令和5年) | ・日本、コロナを 「5類」 扱いへ (5月8日) ・観光業再活性化 (インバウンド) ・値上げ・円安が継続 ・インボイス制度開始 (10月) | ・生成AI (ChatGPT) 急速普及 ・大企業でAI活用実証が進展 ・IT導入支援で士業や外部人材に注目 |
2024年 (令和6年) | ・能登半島地震 (1月1日) ・日銀、マイナス金利解除 (3月) ・「異次元の少子化対策」 始動 | ・生成AIの業務利用が一般化 ・中小企業の業務効率化にChatGPT系統の導入進む ・DX関連補助金が整理・再編される動き |
| 2025年 (令和7年) | ・大阪・関西万博 開催 (4月13日~10月13日) ・「2025年の崖」 問題が顕在化 (?) ・高齢化・地方消滅が本格課題に (?) | ・DX未着手企業の淘汰リスク顕在化 ・政府・民間ともに 「人材育成」 重視へシフト ・ITと業務の融合人材 (シチズンデベロッパー) に期待高まる |
このようなディスカッションがされました📝
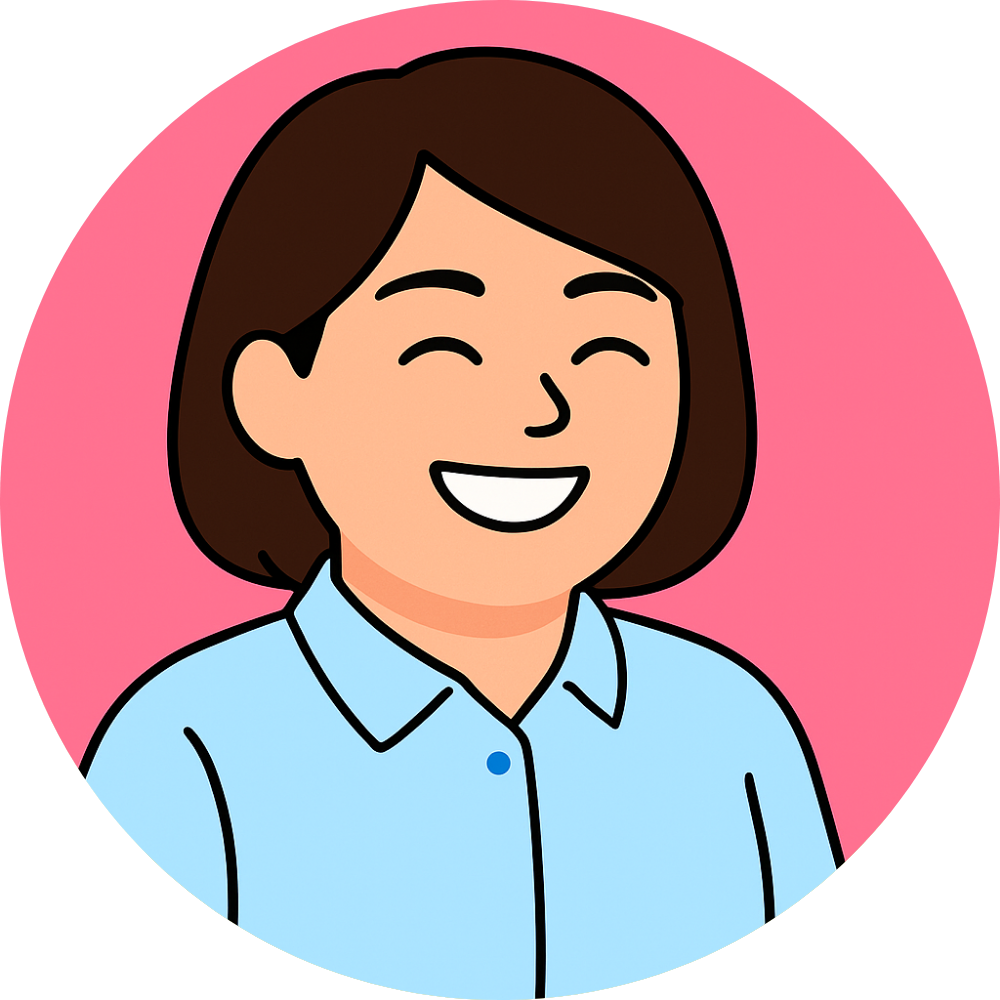
DXの今後の動向について、ご意見を募ったところ 「変化が激しすぎて予測が難しい」 という回答をいただきました。こうした状況のなかで、皆さんはDX化を進めていく難しさを感じる場面はありますか?

私たちの事務所では生成AIを使って議事録作成を自動化し、すぐ顧客に提供できる仕組みを作りはじめました。ただし、セキュリティ面のリスクや社内ルールの整備が追いつかず、もう一歩踏み込めない状況です。

ツールは個人でも簡単に使えるようになっていますが、その分セキュリティ面が一番の心配事となりますね。AIに関しても同様です。

クラウド会計が出始めた頃は、データ保存方法やサーバーの場所などについてお客様から質問されることが多かったんです。でも今はほとんど聞かれなくなりました。世の中的にそれが当たり前になったからだと感じています。生成AIについても、いずれは同じように利便性が不安を上回り、徐々に受け入れられていくのではないでしょうか。

私もそう考えています!そして、お客様との信頼関係が重要な会計事務所としては、「なぜこのシステムを選んだのか」 「どのようなセキュリティ対策をしているのか」 を説明できる状態にしておく必要があるとも感じます。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
生成AIの台頭によって、これまでDXが思うように進まなかった部分が急に後押しされたように感じています。特にお客様側のDX化はAIの力でさらに加速するはずです。
DXという言葉そのものが変化への意識を芽生えさせたこと自体、成果と言えるかもしれません。
最終目的は、会計事務所内の効率化のためのDXに留まらず、
お客様がより良い成果を出せる環境をつくるDXを目指すことです。
お客様と事務所の双方にメリットが得られる環境を作るためには、これからも情報を集め、実践し続けていきたいですね。
まとめ
今回のディスカッションでは、DXという言葉が社会に広く浸透する一方で、各事務所における捉え方や取り組みの深さには差があることが改めて明らかになりました。
「経営としてDX方針を掲げ、浸透させている」 という前向きな声がある反面、
「DXとは何かを模索している」 「手段が目的化してしまっている」 といった課題感も共有されました。
その中でも、テレワークの環境整備、ウェブ会議やクラウド会計の普及といった、業務の進め方そのものが変わった事例は確実に増えています。
ツール導入による効率化や移動・作業時間の削減といった目に見える効果が現れる一方、
DXの本質は単に効率化を図ることではなく、”新しい価値を生み出す” ための変革にあるという認識も改めて強まりました。
生成AIについては、日進月歩で技術革新が進んでいるものの、セキュリティや運用ルールの整備といった課題は依然として残されたままです。
しかし、この技術の急速な浸透は、これまで停滞しがちだった取り組みを後押しし、
DXの推進を加速させる大きな可能性を秘めています。
DXは 「やらされる取り組み」 ではなく、顧客と現場双方の価値を高めるための手段です。
今回の対話から得られた知見や気づきが、各事務所の業務改善や顧客支援の質向上に活かされ、
より持続的なDX推進につながることを願っています。
