イベントレポート 「DXトークセッション:業務の標準化・教育コスト最適化を実現するマニュアル活用法 ━━ 業務の土台から考えるDX推進」
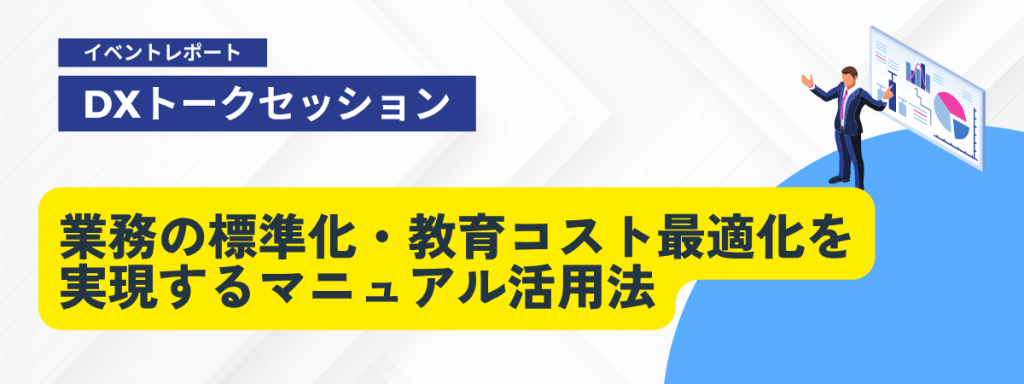
中小企業DX推進研究会では、2025年6月27日に 「業務の標準化・教育コスト最適化を実現するマニュアル活用法」 をテーマに、ディスカッションを行う会員定例勉強会を開催いたしました。
2025年6月27日 (金) 16:30 ~ 17:30 開催
テーマ:業務の標準化・教育コスト最適化を実現するマニュアル活用法
Contents
Q1. 業務の標準化・職員教育における貴所に最も近いスタンスを教えてください
最初の議題では、各事務所の業務の標準化・職員教育における、現在の状況についてが話し合われました。
このようなディスカッションがされました📝
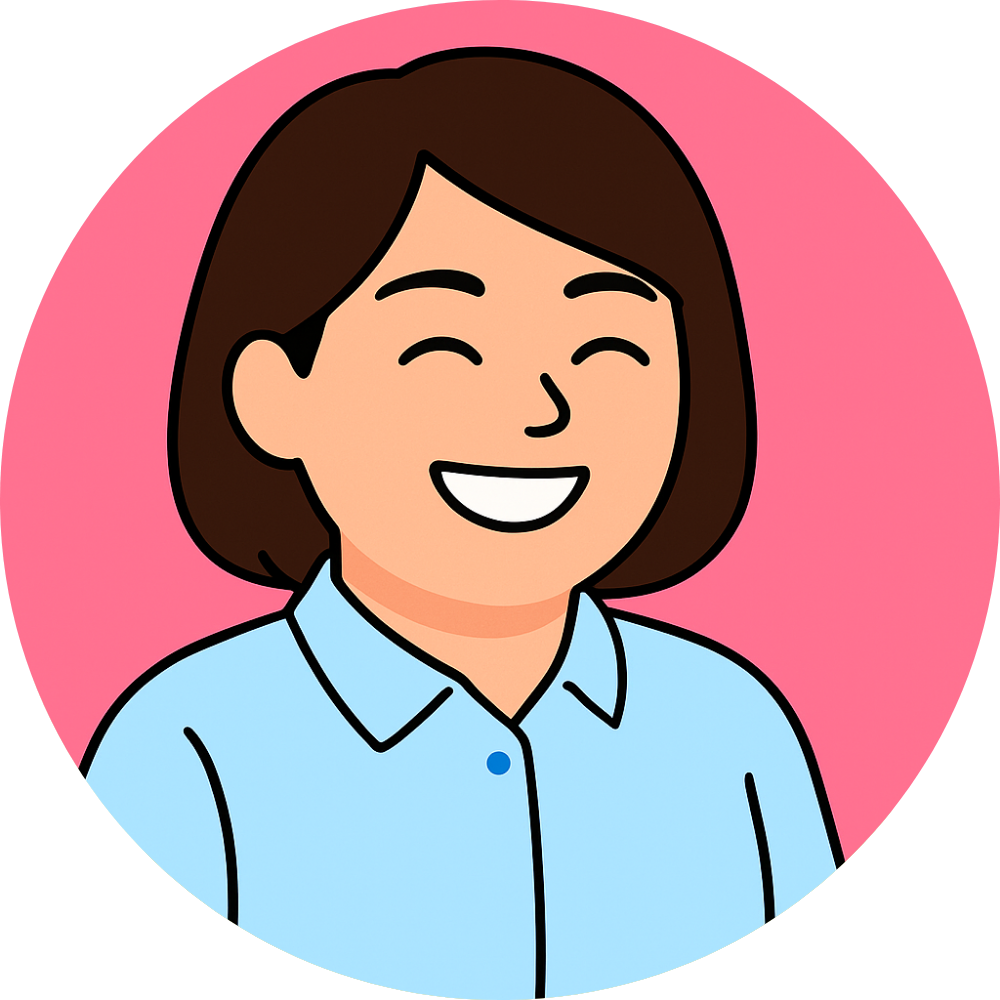
会員の皆さまから事前にいただいたアンケートでは、「基本的には自主的に学んでもらい、都度質問してもらう」 という回答を多くいただきました。

私の事務所も、そのように回答させていただきました。税法というものは難解ですよね。いくら教えても勉強しても腑に落ちにくく、教材となるサイトや本など、根拠を併せて示して指導することを心がけています。それでもなかなかに忘れられてしまうことが多いものです。指導者側にも伝えてみるもののなかなか現場では徹底しきれず、理解が浅くなりがちです。

セブンセンスにおいても、かつてはOJTや本人の自主性に頼る教育スタイルが主流で、マニュアル整備は後回しになりがちでした。マニュアルがあっても更新されず、最新がどこにあるのかも分からない、といった運用上の課題も当時は多く見られましたね。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
かつてセブンセンスでは 「共通の手順書をできるだけ少なく整備し、どのお客様でも使い回す」 という考え方でマニュアルを作っていましたが、実務ではそれが機能しないケースが多くありました。
特に会計事務所の業務は、お客様ごとに細かな対応の違いがあるため、一律の手順ではカバーしきれない場面というものが頻繁に発生します。
もちろん、税務申告の最終チェックのように共通化しやすい工程もありますが、月次の記帳や監査業務などは顧客ごとに注視するポイントも異なります。
そうした中で、私たちがたどり着いたのは 「100社あれば100通りのチェックリストやマニュアルが必要になる」 という結論です。
個別の事情を丁寧にリスト化し、それぞれに合わせた形で仕組み化することが、現実的で効果的な標準化の形だと考えています。
Q2. 現在、利用されている、または注目しているツールを教えてください
次に、所内で利用しているまたは注目している、チェックリスト・マニュアル作成ツールが共有されました。
アンケートでは、以下のようなツールが挙げられていました。
| サービス名 | 主な用途・特徴 |
| Helpdog マニュアル (noco 株式会社) | 旧トースターチーム AIを活⽤した次世代型マニュアル作成ツール |
| Google Sites (Google LLC) | Webサイト作成ツール (社内マニュアルやPJ共有など.. ) YouTubeや地図、スプレッドシートなどGoogleが提供しているサービスを配置できる |
| Teachme Biz (株式会社 スタディスト) | 写真や動画を用いたわかりやすいクラウド型マニュアル 前処理や中間処理はAIが⾏う 「Teachme AI」 もある |
| GROWI (GROWI, Inc.) | マニュアルや企画書の共有、議事録の同時編集など ノウハウの共有・蓄積・活⽤オープンソース |
| アニー (株式会社 関通) | マニュアルとチェックリストの両方の機能をもったクラウド型業務管理ツール |
| kintone (サイボウズ 株式会社) | 業務のシステム化や効率化を実現するアプリが作れるクラウドサービス |
| esa (合同会社 esa) | チャットのように気軽に発信、Wikiのように整理・編集する そのままスライド表示に切り替えられ、会議資料としても活用可能 |
このようなディスカッションがされました📝
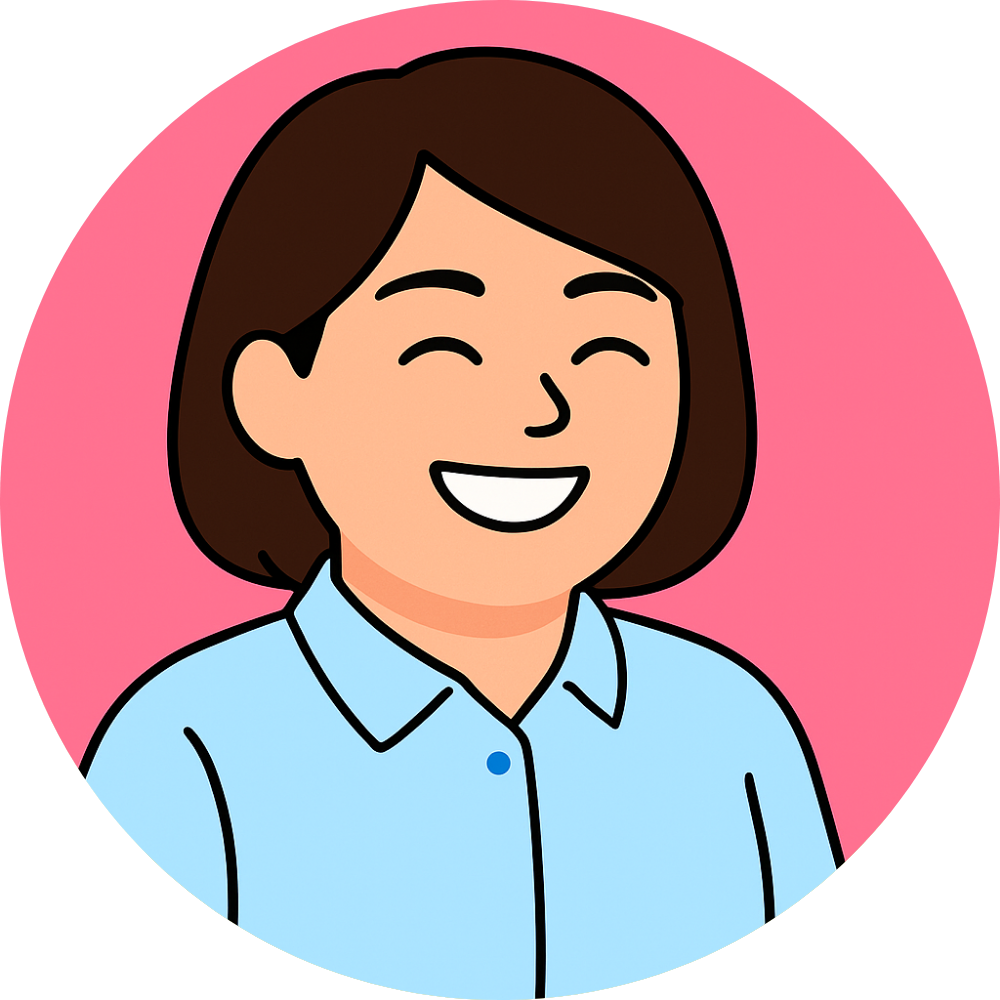
現在、どのようなツールを活用されていますか?

正直まだまだ一部の人しか使いこなせていませんが、Teachme Biz を活用しています。

「活用されるマニュアル」 にするためには、業務の導線の中にあることやアクセスのしやすさ、それから更新のしやすさが大切だと考えていますね。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
マニュアルやチェックリストのツールも多様で、マニュアル作成に特化したものだけでなくWiki形式、業務アプリ型などの種類があります。いずれにおいても大切なのは 「どのツールにするか」 よりも 「どれだけ日常的に開かれるか、使われるか」 という視点です。
いくら高機能を持つツールでも、開かれずに放置されていては意味がありません。私たちの経験でも、マニュアルが更新されない・見られないという課題の多くは、「普段使っている業務環境に紐づいていないこと」 が主な原因でした。
たとえば、Google環境が中心の事務所であれば Google Sites に、kintone を業務で使っているなら kintone にまとめる。そんな具合で、「日々開く習慣のある場所」 へマニュアルを置くこと、それがまず第一歩になります。
そのうえで、ツールごとの特性 (たとえば、Teachme Biz ならスマホ撮影で直感的に作成できる、といった利点) を活かしながら、業務フローの中に自然に導線を敷いておくことが、より実用されるマニュアル作りの鍵だと考えています。
Q3. 課題やお悩みなど、他事務所に聞いてみたいことはありますか?
アンケートでは、以下のような質問が挙げられていました。
・マニュアルよりも直接聞く等の 「がちがちの固定概念は壁になっています」
・更新のタイミングはどのようにしていますか?
・マニュアルを作成する業務の線引きは?
・記帳代行業務の入力手順書 (記載方法など.. )
このようなディスカッションがされました📝
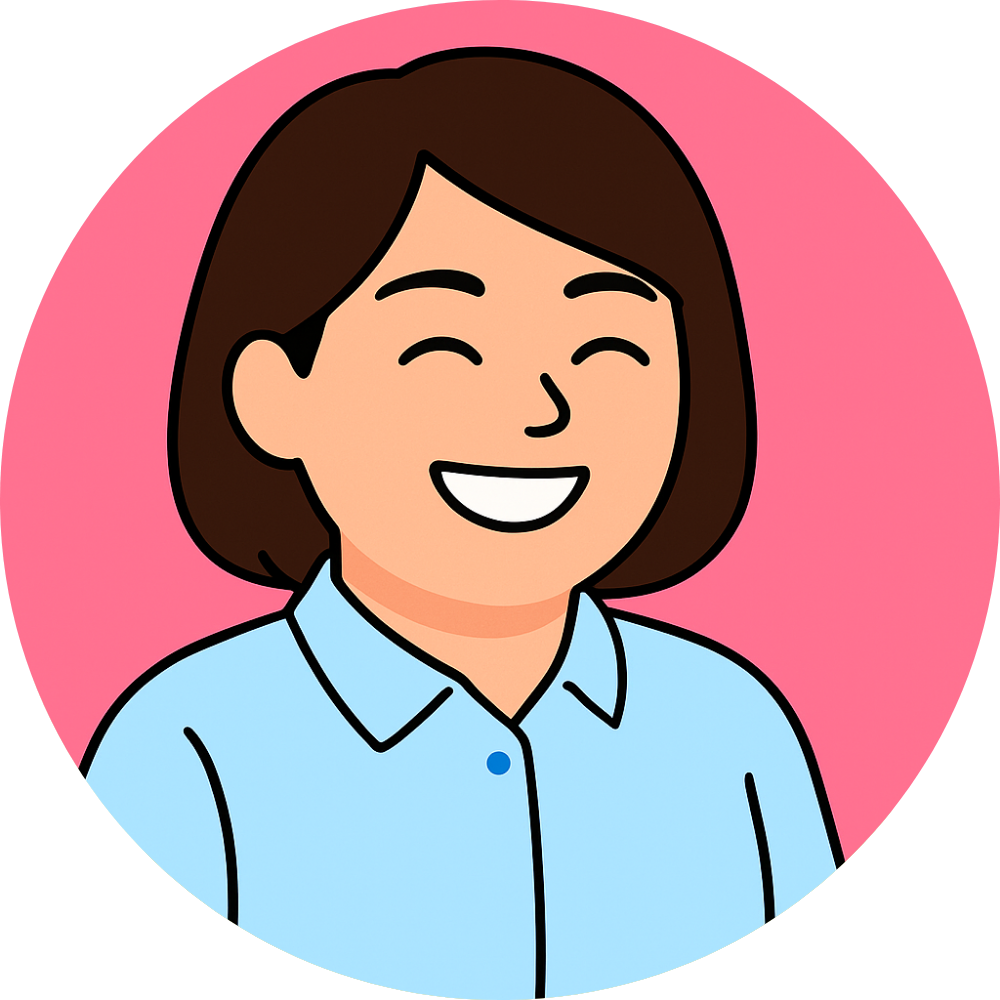
他事務所に聞いてみたいこととして、マニュアルの更新頻度やどんな内容まで記載するかの線引きについてが多く挙げられました。

最初のマニュアルはベテランが作るべきですが、理解度の高いひとの表現だと分かりづらいことも多いでしょう。
だからこそ、若手が実務の中で気づいたタイミングで更新していくような運用が理想ですね。

そうですね。また、特に若手には、マニュアルどおりに作業するだけでなく、「なぜそうするのか?」 という業務フローの理解も大事にしてほしいと感じています。単にチェックをこなすだけではなく、自分の頭で考える習慣も育てたいですね。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
マニュアルやチェックリストは非常に有効なツールですが、使い方を誤ると 「自分で考える力」 を奪ってしまうことがあります。ツールに依存しすぎた結果、トラブル時に対応できなくなってしまう状態は実際に起こり得ます。だからこそ、線引きを考える際にも、「何を残すか」 だけではなく 「どう使うか」 までを含めて整理しておく必要があります。
一方で、マニュアルが整っていることで、急な体調不良や休暇の際にも 「自分にしか分からない仕事」 を抱えることなく安心して引き継ぐことができる、という大きなメリットもあります。ツールは人の代わりではなく、人を支えるための仕組みとして業務の属人化を防ぎつつ、必要な場面でしっかり役立つよう、バランスを意識した運用設計が重要だと感じています。
まとめ
業務の標準化や教育体制の整備に取り組むうえで、マニュアルの準備は非常に有効な手段であると考えます。一方、「カタチだけ整えても運用されない」 、「更新が続かない」 といった悩みを抱える現場も少なくありません。
今回は、実際の導入経験や運用面での工夫、また各事務所ならではのツール活用事例が共有され、「どうすれば “使われるマニュアル” になるのか?」 という視点で多くの気づきが得られました。
属人化を防ぎ、業務の質と再現性を高めるためには、現場の声を反映した柔軟な設計と、メンテナンスを前提とした運用体制の構築が欠かせません。中小企業にとってのDXとは、単なるツール導入ではなく、日々の業務の “土台” を見直す取り組みそのものです。今回の対話から得られた実践的な知見が、読者の皆さまの現場でも役立つヒントとなれば幸いです。
