イベントレポート 「DXトークセッション:生成AI 実際どう使う?現場視点で語らう活用アイデア」
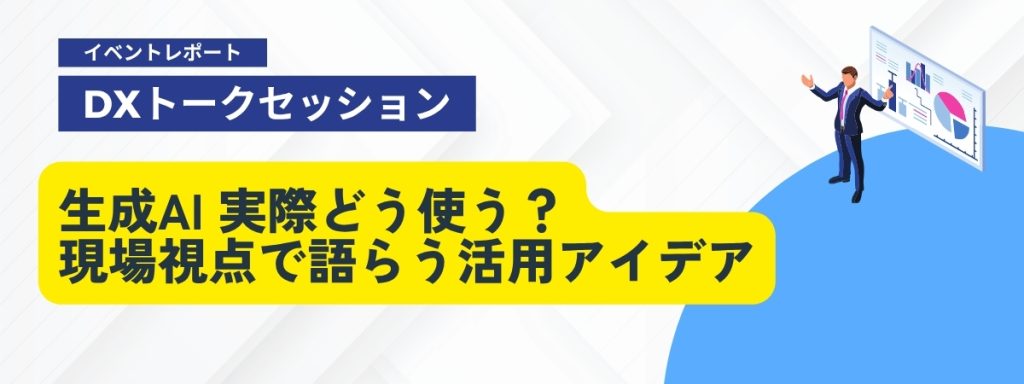
中小企業DX推進研究会では、2025年5月28日に 「生成AI 実際どう使う?現場視点で語らう活用アイデア」 をテーマに、生成AIの活用についてディスカッションを行う会員定例勉強会を開催いたしました。
2025年5 月28 日 (水) 16:30 ~ 17:30 開催
テーマ:生成AI 実際どう使う?現場視点で語らう活用アイデア
Contents
Q1. 現在、生成AIにおいて利用されている、または注目しているツールを教えてください
最初の議題では、生成AIの利用ツールや注目されているサービスについて共有されました。
会員の皆さまから事前にいただいたアンケートでは、以下のような回答がありました。
| サービス名 | 主な用途・特徴 |
| ChatGPT (米国:OpenAI) | 自然な対話、文章生成、翻訳、要約、プログラミング支援など |
| Google Workspace・Gemini (米国:旧・Bard) | Google製品へのAI補助機能 (メール下書き/要約/資料作成など) 画像・コード生成、チャット形式の対話も可能 |
| Microsoft Copilot (米国:Microsoft 365向け) | Office製品に統合、文書作成や表計算 自動要約・分析・提案などを支援 |
| Notta AI (日本:Notta 株式会社) | 会議録音の文字起こし、要約、翻訳、タスク抽出など 議事録サービス |
| イルシル (日本:株式会社 イルシル) | AI搭載スライド自動生成サービス |
| Perplexity (米国:Perplexity AI) | AIによる検索支援ツール (ソース付きの簡潔な回答を提示) |
| Google NotebookLM (米国:Google) | アップロードしたドキュメントを基とした要約・質問応答 アイデア出しのサポートなど自分専用のAI リサーチアシスタント |
このようなディスカッションがされました📝
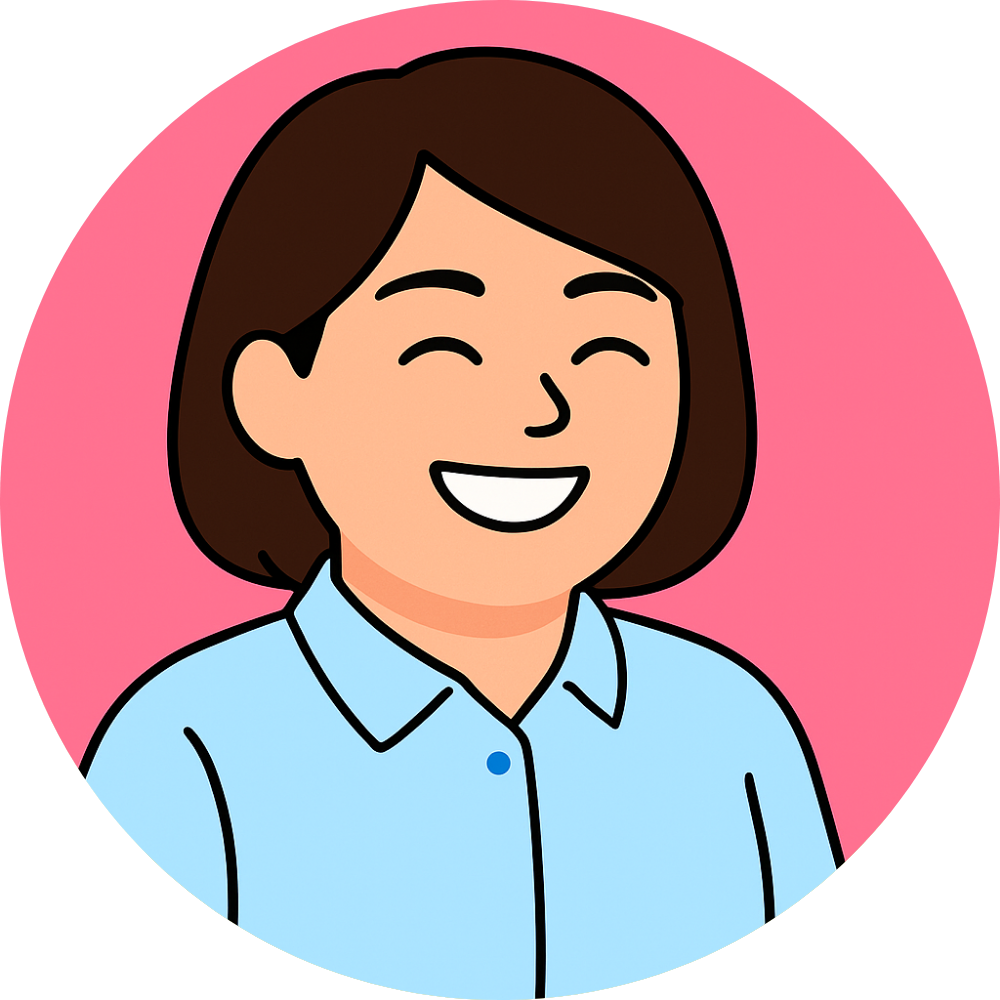
山口会長、いくつもあるツールのなかでどちらを使えばいいのか、使い分けはどのようにすればいいのか迷いますよね..

どの生成AIツールを使うかは車のメーカーを選ぶようなもので、大きな違いはないと考えています。
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
それぞれのAIツールには得意分野や特徴はありますが、それほど大きな違いはないものと考えています。Canvaのように画像生成やデザインに特化したもの、イルシルのようにスライド作成に強いツールなど、業務ごとの用途特化型AIもありますので、ツールの特徴を理解して、用途に応じて使い分けるのが重要です。
また、生成AIのツール選びは〈何ができるか〉よりも、〈誰がどこで使うか〉で決めるのが自然だと思います。例えば、Google環境で仕事をしている人ならGemini、Microsoft環境ならCopilot、MacユーザーはChatGPTが使いやすい.. と感じるかもしれません。『どれが一番』ではなく、『どのツールが自分の業務や思考スタイルにフィットするか』。この視点を持つだけで、ツール選びが一気に楽になるはずです。
Q2. 現在、生成AIにおいて利用されている場面を教えてください
次に、生成AIが現在どのような場面で活用されているかについて共有されました。
アンケートでは、以下のような活用場面が挙げられていました。
・MAS監査 (資料作成、会議の文字起こし~議事録作成、システム開発)
・資料作成時、議事録作成
・企画案検討
・文章作成
このようなディスカッションがされました📝
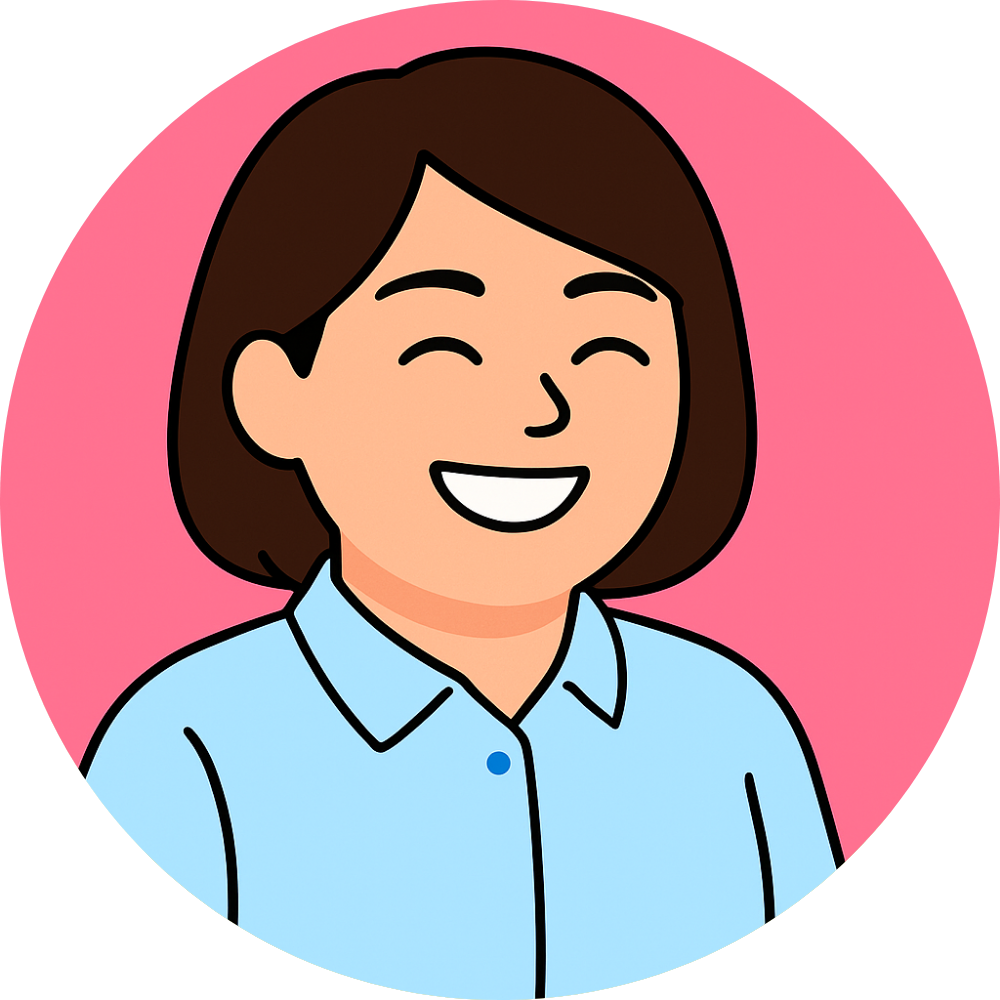
これらの活用事例をみて感じるポイントはありますか?

やはり資料作成やメール文面の下書きのような〈目に見える作業〉にこそ、まず使ってみる価値がありますよね!
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
たとえば、議事録の要点整理や社内マニュアルの下書き作成などには非常に時短効果がありますよね。
生成AIは〈ゼロから何かを考える作業〉よりも〈何かをもとに整理・変換する作業〉を得意としています。だからこそ、ゼロから文章を作成させるのではなく、もととなる要約文を生成AIに読み込ませて成形させるような〈補助作業〉から着手するのが現実的だと思います。
Q3. 「生成AI」 でこんなことしてみたい、こんなことできそうだ、と思うことはありますか?
最後の議題では、「生成AIでやってみたいこと」 「今後できそうだと期待していること」 について。
アンケートでは、以下のような期待が挙げられていました。
・通帳コピーからの仕訳
・領収書からの仕訳
・医療費集計
・試算表の説明
・専属のメンターになってもらいたい
・月次チェックや消費税チェック
・業務改善
このようなディスカッションがされました📝
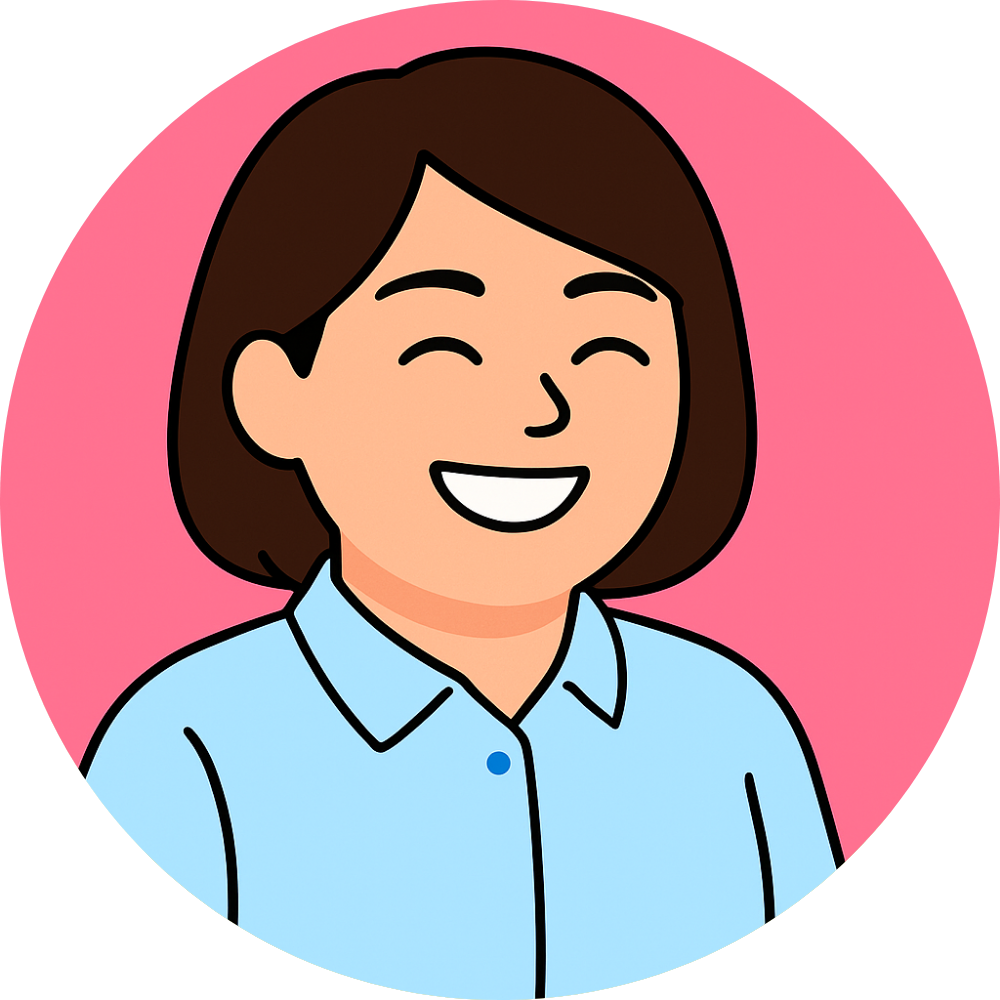
山口会長、さまざまなアイデアをお寄せいただきました!

どれもこれもワクワクするものですね!その中でも導入のハードルが低そうなのは..
中小企業DX推進研究会会長 山口の見解
この中で比較的使いやすく、導入のハードルが低いのは、「試算表の説明」 や 「専属メンター」 のような使い方かと感じます。
こうした〈説明系〉の用途においては、プロンプトを細かく作り込まなくても、ある程度満足のいく回答が返ってくるので実用的です。
一方で、仕訳作成などの〈実務処理〉となると、現時点では精度の高いアウトプットを得るためには、かなり細かな指示や設定が必要です。設定が不十分だと、結局手作業の方が早くなってしまう可能性もあり、実用面ではまだまだ課題が残っています。ただ、最近はAIが元になる情報を読み込んで、自動で推論してくれるレベルにまで進化してきているので、資料をアップロードするだけでスムーズに仕訳が生成できる時代は近いと思っています。
また、チェック作業というのはAIが得意な分野です。たとえば前月との比較や、仕訳を使った消費税チェックなどは、ルールが明確なのでAIでも精度よく対応できる可能性が高いですね。
まとめ
このあとも事前アンケートからのディスカッションのほか、NotebookLM の日本語による音声概要機能やClaude(クロード) のデモンストレーションをご覧いただきました。
今回の勉強会では、生成AIをどのように活用するか、その選び方や使い方について多角的な意見が交わされました。
「どのツールを選ぶか」 以上に、「何のために活用するのか」 「どこで業務に組み込むか」 といった視点が重要であることが再確認されました。
また最近では、AIを活用して、各自が記録した情報を自動で集約・整理する仕組みづくりにも注目が集まっています。
ツールやフォーマットに縛られず、自由に入力した情報をもとにAIが進捗管理表を生成する――そんな新しい選択肢も見えはじめています。
生成AIの進化はスピーディで、常に新たな知見や機能が至るところで生まれています。最新の情報を追いかけながらアップデートを怠らず、柔軟な試行錯誤を重ねていくことは、時代を切り拓く鍵になるかもしれませんね。
